チャーリー・へブドのテロ事件に次いで、アーサー・アセラフ氏がアルジェリアにおけるフランス植民地支配のダブル・スタンダードについて語る

2015年1月にパリのチャーリー・へブド社で起きたテロ事件をきっかけに言論の自由(free speech)とフランス国内外におけるその限界について激しい討論が巻き起こった。1980年代に問題となった、小説『悪魔の詩』を取り巻く議論にそって討論は進んだが、今度の事件は現場がフランスなのではるかに強い象徴性を帯びたのである。啓蒙主義の生地、そして詩人ヴォルテールの故郷でもあり人権理念を生んだフランスが、新たな脅威を感じたのである。フランス全土で400万人ものデモンストレーターたちが波立つ2015年1月11日の行進のスローガンは、共和国制の価値観を奨励するものだった。後ほど政府は、国内の教育機関で国の若者たちに共和国制の大切さを教授する大規模な講義要項を実施した。
実際、共和国制が問題のないスローガンか否か疑問視する者は少なかった。詰まるところ、19世紀以来フランスは巨大なムスリム系人口を支配し続け、植民地時代には彼らに言論の自由(freedom of speech)を与えていなかった。言論の自由が共和国制的、フランス的、それとも西洋的な概念なのか定義する前に、まず歴史を考慮する必要がある。
2015年現在でも使われているフランスの報道の自由(freedom of the press)に関する法律は、1881年7月29日にできたものだ。当時、この法律は共和国のムスリム系住民には適用されなかった。法律は、特にアルジェリアや他の植民地に在住するフランス市民を守ると同時に(69条)、フランスの植民地で支配されている住民たちを対象とはしなかった。これはただのミスではなかった。法案通過一ヶ月前の1881年6月28日に同議会が原住民 (indigénat) に関する決定的な法律を採決した。植民地特殊法という、奇妙な二重制度によって、現地住民は権力者に対する言論の自由、集会の自由、出版の自由を禁じられた。原住民法 (indigénat law) は適正手続を無視し、裁判を要求せず、多様な罰金や刑罰を原住民に課した。結局、フランスでは言論の自由(freedom of speech)が法制化されると同時に、その自由は海外に住む共和国の多くの住民に禁じられたのである。彼らは、近代の市民権の恩恵に値しない人種だと認定されたのだ。
1881年の法律はアフリカやアジアを含むフランス植民地帝国に住む多様な宗教を信仰する住民を言論の自由から排除しているが、アルジェリアの例は、ムスリム系を攻撃目標にしているという点で、特に教訓的だといえる。植民地下のアルジェリアでは、一部の例を除いて、ムスリム系ではないということで「市民」を定義していた。ムスリムとは、宗教的な意味合いを外して純粋に人種的なカテゴリーとして評価されていた。例えば、馬鹿げた話ではあるが、いくつかの裁判の例をとれば、原住民はキリスト教に改宗しても法的にはムスリムでありつづけ、従って差別的な法律を課され市民権の枠内から外されていた。
アルジェリアは正式にフランス国家の一部であったため、1871年のアルジェリア系ユダヤ人のフランス市民権獲得に伴って、多少なりとも思い通りに政府を批判するような新聞を提供する出版業界が発達した。一方でムスリムは、センサーシップと脅しにおびえ、アルジェリア人によって記述されたアルジェリア人のための新聞は20世紀初頭にようやく出版されるようになったが、1962年の独立まで日刊新聞は存在しなかった。もしムスリム系の人々が少しでも、官僚たちによるマイナーな汚職事件について批判するような声を上げたならば、彼は収容されるか裁判なしで国外追放になったであろう。
残酷な征服戦争の後、「支配された」ムスリム系人民は、フランスに対して反乱を起こしかねないとされ、政府にとって自由に発言されては困る存在であった。政教分離に関わる有名な1905年の法律は、アルジェリアにも適用されるはずだったが、結局されなかった。フランス国家は、1962年の独立までイマームを任命し監督し続けた。
要するに、フランスにおける報道の自由の到来は、植民地化の暴力、イスラム嫌悪、そして植民地支配が呼び起こす人種差別の発生と重なったのである。
フランスは、報道の自由に関して全く問題をかかえなかったことはない。ましてムスリム系との関係ではなおさらそうである。植民地下のアルジェリアにおける問題は、ムスリム教徒が共和主義的価値へ協調できなかったことではない。逆に、問題は以下の通りである。つまり、フランスでの法形成がムスリム系人民の発言力を奪い、2015年の近代都市化したフランスで効力を発しているという点だ。こうした背景から鑑みると、チャーリー・へブドのテロ事件後、フランスの地元メディアや海外メディアが「統合」と「ムスリムと共和国の協調性」についてこぞって議論している姿が滑稽に思えてくる。我々は、ムスリム系の人々に言論の自由の価値(values of free speech)への理解を深めるよう求める以前に、過去に同様の言論の自由論を使って彼らを疎外した歴史を思い出すべきだ。
以上の歴史が2015年1月の恐ろしい事件を解説すると言う訳ではない。カウアチ(Kouachi)兄弟の祖先はアルジェリア出身だったかもしれないが、生まれはパリ、特訓はイエメンでされた。自分たちでプロパガンダを行なうなかで兄弟は一度も植民地主義やアルジェリアについて語っていない。知識人にとってはジハードよりもはるかにこれら(植民地主義のなごり)の原因が興味深い。歴史を回想するのはジハーティストに言い訳・許しを与えることに繋がらない。歴史の回想は彼らを敗北させ、この事件が純粋なフランスと後退化するイスラムの闘いではないことを我々に伝えてくれる。
虐殺にいかに反応するべきか探りながらも、今日の事情に適切な「言論の自由(free speech)」の定義を探求するなか、我々に必然的なのは過去に使われた言論の自由とその利用法(差別、除外、監視としての役割)について再考する試みである。言論の自由が「共和主義的」、「フランス的」、それとも「西洋的」であると主張し、神話の世界にまみれた権威的な啓蒙主義時代の人物像を呼び起こしても、より差別のない開放的な社会の建設には到底及ばないのである。
著者:アーサー・アセラフ(Arthur Asseraf)、オックスフォード大学・オール・ソールズ・カレッジ教授







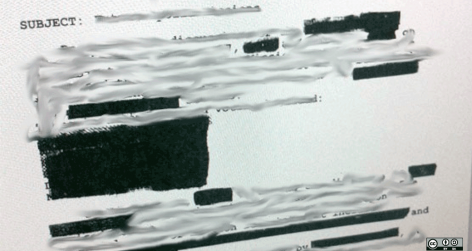


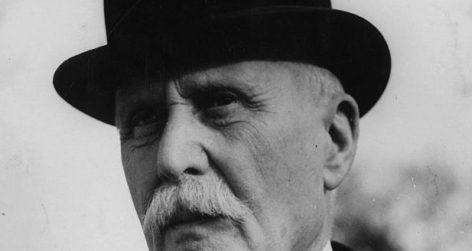

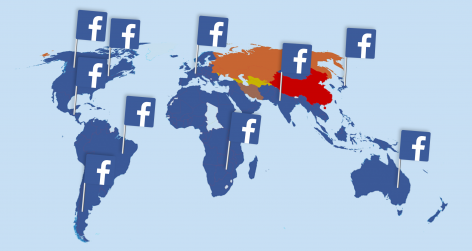


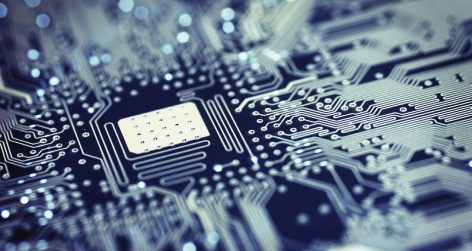







reply report Report comment
Merci infiniment pour cet article qui remet enfin en question cette idée d’une France ‘pure’ qui incarne la liberté et les droits de l’Homme. La Rochefoucauld disait “les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n’était que d’un côté.” Je crois qu’il est extrêmement malhonnête et dangereux de refuser de voir les torts de toutes les parties dans cette querelle qui, en effet, dure depuis si longtemps… Pour apporter de l’eau au moulin d’Arthur Asseraf, j’ajouterai que l’Islam rétrograde souvent décrié en France se base tout de même sur un livre, le Coran (ou Qurʿān si l’on applique une translitération correcte), qui au VIIIème siècle déjà, alors que la France faisait ses premiers pas, encourageait ses adversaires à le critiquer en produisant des vers aussi éloquents (cf. Q. 2:23 et 11:13).